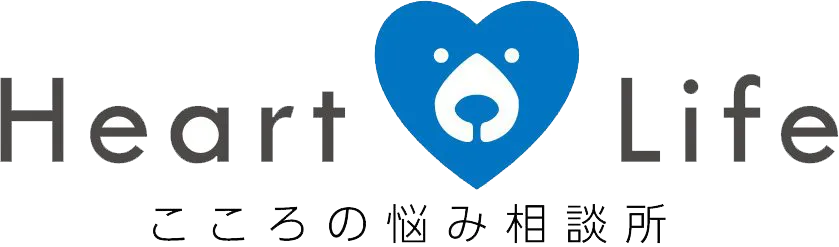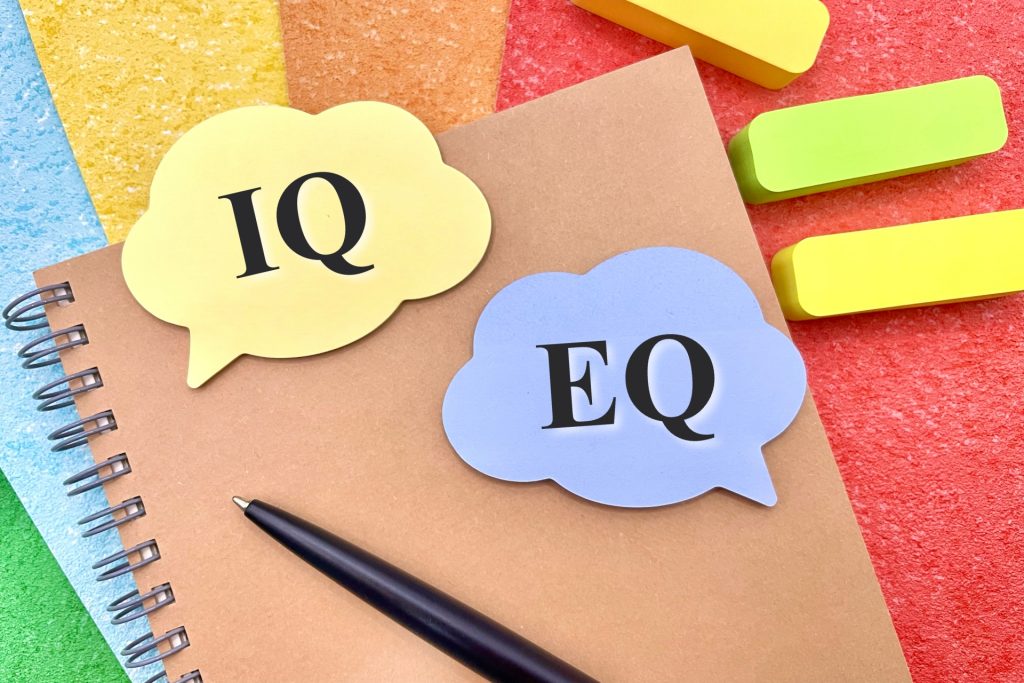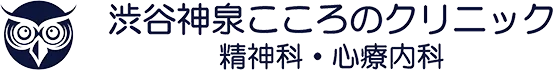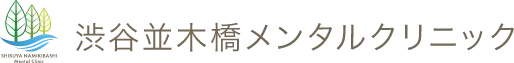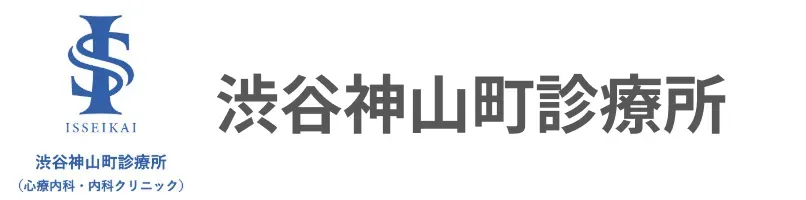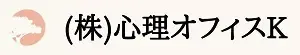「他の人なら気にならないような些細なことが、ずっと頭から離れない」 「人混みや騒がしい場所に行くと、ぐったりと疲れてしまう」 「相手の表情や声のトーンから、感情を読み取りすぎて気疲れしてしまう」
もし、あなたがこのような感覚を日常的に抱いているのなら、それはあなたが「HSP(Highly Sensitive Person)」という繊細で敏感な気質を持っているからかもしれません。そして、その人一倍の疲れやすさの背景には、絶えず情報を処理し続けることによる「脳疲労」が隠れている可能性があります。
HSPは病気ではなく、生まれ持った個性の一つです。しかし、その繊細さゆえに、脳が処理する情報量が人よりも多くなりがちで、知らず知らずのうちに脳がエネルギー切れを起こしてしまうことがあります。
この記事では、HSPという気質の基本的な特徴から、なぜ脳疲労を起こしやすいのか、その関係性を詳しく解説します。さらに、つらい脳疲労の症状を和らげるための、今日からすぐに実践できる具体的なセルフケア方法もご紹介します。
HSPとは?
[1] HSPとは、「Highly Sensitive Person(ハイリー・センシティブ・パーソン)」の頭文字をとった言葉で、日本語では「非常に感受性が強く、敏感な気質を持った人」と訳されます。これは、アメリカの心理学者であるエレイン・アーロン博士によって提唱された概念で、病気や障がいではなく、生まれ持った気質の一つとされています。
統計的には、人口の約15〜20%、つまり5人に1人程度がHSPの気質を持つと言われています。HSPの人たちは、周囲の環境からの刺激に対して非常に敏感で、他の人が気づかないような些細な音や光、匂い、あるいは人の感情の機微などを敏感に察知する能力に長けています。これは、情報を処理する脳の神経システムが、非HSPの人とは異なる働きをすることが原因と考えられています。その繊細さゆえに、様々な情報を深く処理するため、疲れやすい傾向があるのです。
HSPの特徴
エレイン・アーロン博士は、HSPに共通する特徴として「DOES(ダズ)」という4つの頭文字で表される概念を提唱しています。これら4つの特徴すべてに当てはまる場合、HSPである可能性が高いとされています。
関連記事:HSPの特徴とは?カウンセリングで治療できるのかも解説
考えすぎてしまう
「DOES(ダズ)」の「D」は、「Depth of processing(深く処理する)」を意味します。物事をじっくりと考え、深く情報を処理するのが特徴です。例えば、何かを決断する際には、あらゆる可能性をシミュレーションし、メリット・デメリットを徹底的に比較検討するため、時間がかかってしまうことがあります。また、友人との何気ない会話の後でも、「あの時、あんなことを言って相手を傷つけてしまったのではないか」などと、一人で深く考え込んでしまう傾向があります。
関連記事:HSPの人間関係がうまくいかない理由と対処法を解説
外部の刺激を受けやすい
「O」は、「Overstimulation(過剰に刺激を受けやすい)」を指します。HSPの人は、五感が鋭敏であるため、外部からの刺激に非常に敏感です。人混みのざわめきや、強い光、大きな音、特定の匂い、あるいは服のタグが肌に触れる感覚など、他の人が気にも留めないような刺激に対して、過剰なストレスを感じてしまうことがあります。多くの情報や刺激が一度に入ってくると、脳が情報を処理しきれずに、疲弊してしまいやすいのです。
感情の反応が強い
「E」は、「Emotional reactivity and high Empathy(感情の反応が強く、共感力が高い)」ことを示します。HSPの人は、他人の感情に深く共感する能力に長けています。相手の喜びや悲しみを、まるで自分のことのように感じ取ってしまうため、感動的な映画や音楽に人一倍心を揺さぶられます。その反面、他人が怒られていたり、悲しんでいたりする場にいると、自分までつらくなってしまうなど、感情的な影響を受けやすく、気疲れしやすい側面も持っています。
小さな違いに気づきやすい
最後の「S」は、「Sensitivity to subtleties(ささいな刺激を察知する)」です。HSPの人は、周囲の環境の小さな変化によく気づきます。例えば、部屋の模様替えや、人の髪型のわずかな変化、あるいは会話中の相手の表情や声のトーンの微妙な違いなどを、敏感に察知します。この鋭い観察力は、危機管理能力や、人の気持ちを細やかに汲み取る力に繋がる一方で、常に周囲にアンテナを張り巡らせている状態であるため、脳が休まる暇なく働き続けてしまう原因にもなります。
HSPは脳疲労を起こしやすい?
[2] 結論から言うと、HSPの気質を持つ人は、非HSPの人に比べて「脳疲労」を起こしやすい傾向にあります。
人間の脳は、重さこそ体重の2%程度ですが、体全体のエネルギーの約20%を消費する、非常に燃費の悪い器官です。特に、何かを考えたり、情報を処理したりする際に、脳は大量のエネルギーを必要とします。
HSPの人は、前述の「DOES」という特性により、常に脳がフル回転している状態にあります。外部からの光や音といった感覚情報だけでなく、他人の感情やその場の雰囲気といった非言語的な情報まで、あらゆる刺激を無意識のうちに深く、そして詳細に処理し続けています。
例えば、普通の会議に出席しているだけでも、HSPの人の脳内では、「Aさんの声のトーンがいつもより低いのは、何か不満があるからだろうか」「Bさんの資料の誤字は、指摘すべきか、後でこっそり伝えるべきか」「窓の外の工事の音が気になって、話に集中できない」といった、膨大な情報処理が同時に行われています。
このように、非HSPの人よりも脳の活動量が多く、エネルギー消費が激しいため、脳がガス欠状態、すなわち「脳疲労」に陥りやすいのです。HSPの人が感じる慢性的な疲れやだるさは、単なる気分の問題ではなく、脳のエネルギー不足に起因する、れっきとした身体的な反応であると言えます。
関連記事:【HSPあるある9選】繊細さと上手に付き合う方法と強み
脳疲労が引き起こす主な症状
[3] 脳疲労は、私たちの心と体に様々な不調となって現れます。
もし以下のような症状に複数当てはまる場合は、あなたの脳が休息を求めているサインかもしれません。
身体的な症状としては、「頭が重い、ズキズキする」「肩や首の凝りが取れない」「目が疲れやすい、視界がかすむ」「めまいや立ちくらみがする」「なかなか寝付けない、夜中に何度も目が覚める」「朝、すっきりと起きられない」「常に体がだるく、倦怠感が抜けない」などが挙げられます。
精神的な症状としては、「集中力が続かず、仕事や家事でミスが増える」「新しいことを覚えるのが億劫になる」「物事への興味や関心が薄れる」「ささいなことでイライラしたり、不安になったりする」「何をするにもやる気が出ない」といった状態が現れやすくなります。
これらの症状は、脳の司令塔である前頭前野の機能が、エネルギー不足によって低下することが原因で引き起こされると考えられています。
関連記事:HSPの限界サイン9つとタイプ別・性別による限界サインを解説
脳疲労を緩和する方法
[4] HSPの気質そのものを変えることはできませんが、脳疲労を和らげ、心穏やかに過ごすためのセルフケアは可能です。ここでは、今日からすぐに始められる4つの簡単な方法を紹介します。
ブドウ糖を摂取する
脳がエネルギー源として直接利用できるのは、基本的に「ブドウ糖」だけです。脳が疲れていると感じたときには、ブドウ糖を適度に摂取することで、脳の働きを一時的に回復させる効果が期待できます。ラムネ菓子や、果物、ハチミツなどは、ブドウ糖を手軽に補給できる食品です。仕事や勉強の合間など、集中力が切れてきたと感じたときに、少し口にすると良いでしょう。ただし、糖分の摂りすぎは血糖値の乱高下を招き、かえって体調を崩す原因にもなるため、あくまで適量を心がけることが大切です。
瞑想をする
瞑想、特に「マインドフルネス瞑想」は、脳を休息させるのに非常に効果的な方法です。瞑想は、意識を「今、この瞬間」の感覚に向けることで、過去の後悔や未来への不安といった、頭の中を駆け巡る雑念(思考の暴走)を鎮めるトレーニングです。静かな場所で楽な姿勢をとり、目を閉じて、ただ自分の呼吸に意識を集中します。雑念が浮かんできても、それを追い払おうとせず、「雑念が浮かんだな」と客観的に観察し、再び意識を呼吸に戻します。1日5分でも続けることで、脳のデフォルト・モード・ネットワーク(DMN)と呼ばれる、脳のアイドリング状態での過剰な活動を抑制し、脳を意図的に休ませることができます。
自然に触れる
公園を散歩したり、森林浴をしたり、ただ窓から空を眺めたりするだけでも、脳疲労を和らげる効果があることが科学的にも証明されています。自然の中に身を置くと、木々の緑や鳥のさえずり、川のせせらぎといった、都会の人工的な刺激とは異なる「ゆらぎ」のある刺激が、脳をリラックスさせます。また、日光を浴びることで、精神を安定させる働きのある神経伝達物質「セロトニン」の分泌が促されます。頭が疲れたと感じたら、少しの間でも意識的に自然に触れる時間を作ることが、脳のリフレッシュに繋がります。
スマホを見る時間を減らす
スマートフォンやパソコンは非常に便利なツールですが、その画面からは常に膨大な情報が流れ込んできます。特にSNSやニュースサイトを漫然と眺めていると、脳は無意識のうちに情報を処理し続け、疲弊してしまいます。また、就寝前にスマホのブルーライトを浴びることは、睡眠の質を低下させ、脳の回復を妨げる原因にもなります。意識的にスマホを触らない時間、「デジタルデトックス」の時間を作ることが重要です。例えば、「食事中や就寝1時間前はスマホを見ない」「休日の午前中は電源を切っておく」など、自分なりのルールを決めて、脳を情報過多の状態から解放してあげましょう。
脳疲労を放置するリスク
[5] 慢性的な脳疲労は、単なる「疲れ」では済まされない、心身の健康を脅かす深刻なリスクをはらんでいます。
運動不足や肥満になりやすい
脳疲労が続くと、思考力や判断力だけでなく、意欲や行動を司る脳の機能も低下します。その結果、「運動するのが億劫だ」「外に出るのが面倒だ」と感じるようになり、身体を動かす機会が減ってしまいます。この活動量の低下は、基礎代謝の減少や消費カロリーの減少に繋がり、肥満や生活習慣病のリスクを高める原因となります。また、ストレスから食欲が増し、過食に走ってしまうケースも少なくありません。
精神疾患になりやすい
脳疲労の状態は、脳が慢性的なストレスに晒されている状態と同じです。この状態が長く続くと、脳内の神経伝達物質のバランスが崩れ、うつ病や不安障害といった精神疾患を発症するリスクが高まります。特にHSPの人は、元々ストレスを感じやすい気質であるため、脳疲労を放置することは非常に危険です。最初は軽微な意欲低下や気分の落ち込みであっても、それが長期化・深刻化する前に、適切な休息とケアを行うことが何よりも大切です。
時には専門家の力も借りてHSPと向き合うのが大事
HSPの繊細で敏感な気質は、素晴らしい才能であると同時に、脳に大きな負担をかけてしまう側面も持っています。あなたが感じる日々の疲れは、決して気のせいでも、怠けているからでもありません。それは、あなたの脳が人一倍働き、世界を深く感じ取っている証拠なのです。
大切なのは、その特性を理解し、自分の脳をいたわる方法を知ることです。今回ご紹介したセルフケアを、ぜひ日常生活の中に取り入れてみてください。すぐに劇的な変化はなくても、続けるうちに、少しずつ心と体が軽くなっていくのを感じられるはずです。
しかし、セルフケアを試してもなかなか改善が見られない場合や、一人で抱え込むのがつらいと感じる時には、決して無理をしないでください。専門家の力を借りることも、自分を大切にするための有効な選択肢の一つです。
「HeartLife~こころの悩み相談所~」では、HSPの気質を深く理解した経験豊富なカウンセラーが、あなたの悩みに優しく寄り添います。脳疲労の根本にあるストレスの原因を一緒に探ったり、あなたに合ったリラックス方法を見つけたりと、専門的な視点から、あなたが自分らしく、穏やかに過ごせるようになるためのお手伝いをさせていただきます。まずは、あなたの心の内を、安心してお話しに来てみませんか。
この記事の監修者

横浜国立大学大学院臨床心理学専修卒業。卒業後、東京都市教育センターで発達に関する相談業務に従事。その後、神奈川県内の心療内科クリニックで心理士業務、東京都内心療内科・心理カウンセリングルームの心理士勤務を経て、2020年6月、渋谷・心理カウンセリングルーム「Heart Life~こころの悩み相談所~」を開業。2024年3月に「Heart Life~こころの悩み相談所~新宿店」を開業。
<公式SNS>YouTubeアカウント:「心理カウンセラー【臨床心理士】がうつ病について語るCh」
公式Twitter
公式Instagram