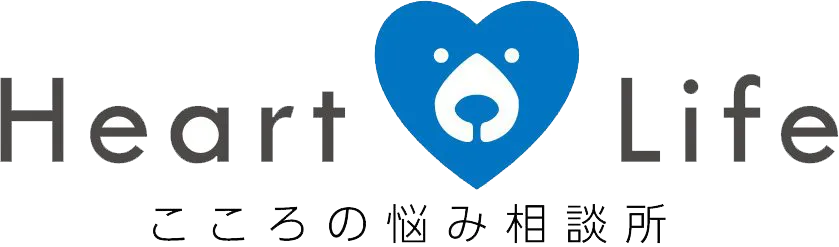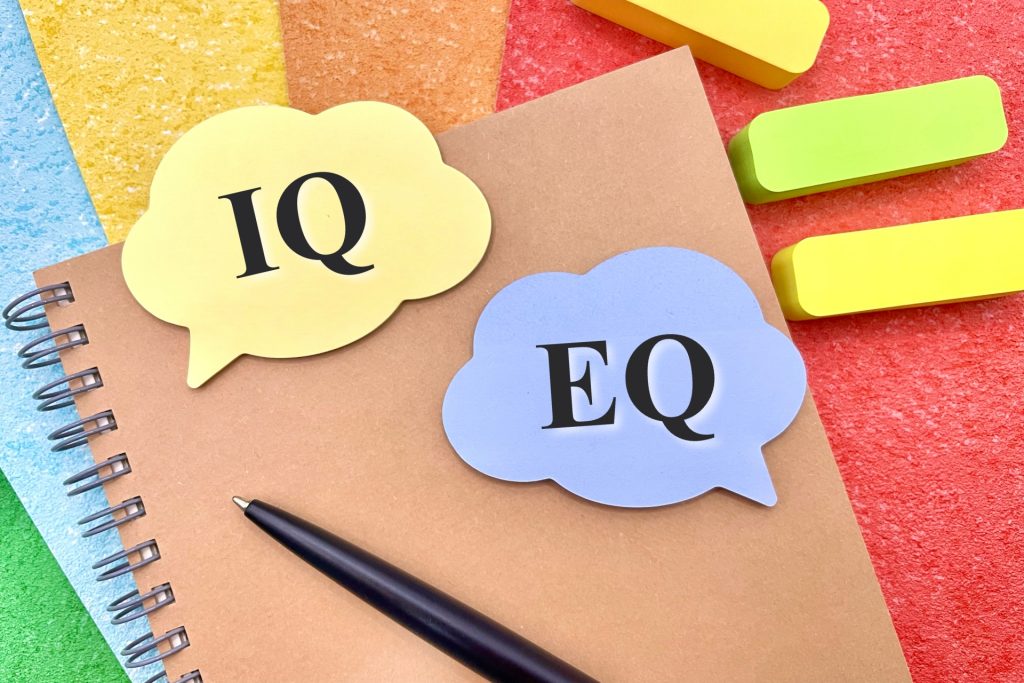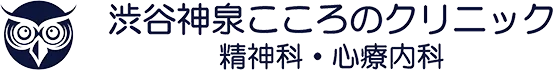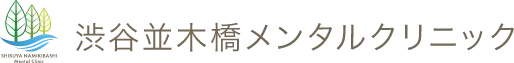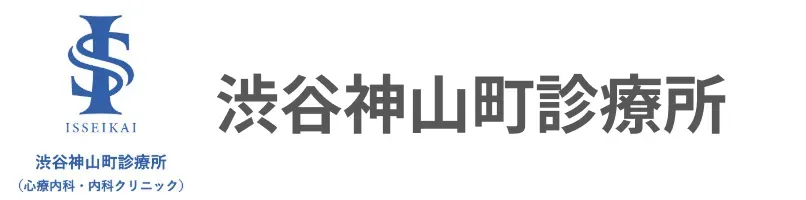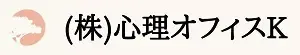お子さまの個性に合ったサポートをしたいと考え、WISC検査を検討している方もいるのではないでしょうか。
専門的な検査だからこそ「何が分かるの?」「うちの子にとって本当に必要?」など、多くの疑問や不安を感じるかもしれません。
本記事では、WISC検査の目的や具体的な内容、メリット・デメリットを分かりやすく解説します。
検査への理解を深めるきっかけとして、ぜひ最後までご覧ください。
WISC(ウィスク)検査で何が分かる?
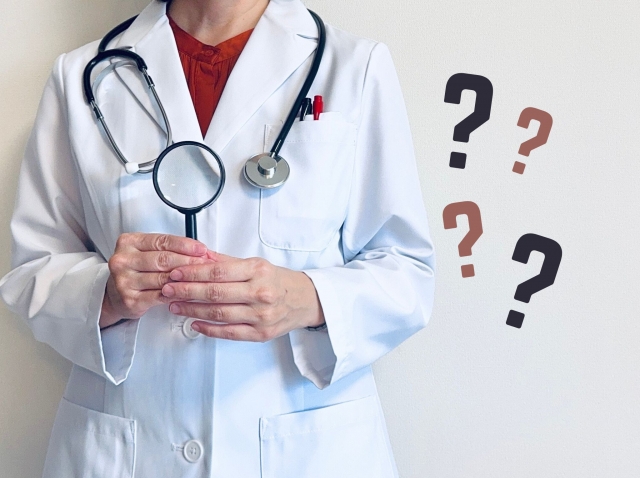
WISC検査は、子どもの発達や認知能力を客観的に理解するための検査です。
知能指数(IQ)という言葉だけが先行しがちですが、実際には子どもの多様な側面を見つめられます。
ここでは、WISC検査の基本的な特徴を以下3つ解説します。
- ウェクスラー式知能検査は世界標準の評価ツール
- WISC-IVとWISC-Vでは対象年齢と検査内容が異なる
- 5つの指標と全検査IQで認知能力を多面的に評価できる
これらを知ることでWISC検査がどのようなものか、全体像が見えてくるでしょう。
ウェクスラー式知能検査は世界標準の評価ツール
WISC検査は、世界中で広く使われている信頼性の高い知能検査です。
心理学者デビッド・ウェクスラーによって開発された「ウェクスラー式知能検査」の1つであり、長い歴史と多くの実績があります。
この検査は、単にIQという1つの数値で能力を測るものではありません。
言葉の力や目で見たものを処理する力など、さまざまな側面から子どもの認知能力を評価します。
世界中の教育現場や医療機関で活用されており、子どもの発達を客観的かつ多角的に把握するための世界標準のツールといえるでしょう。
WISC-IVとWISC-Vでは対象年齢と検査内容が異なる
WISC検査には改訂版があり、現在主流の「WISC-V」と、広く普及している「WISC-IV」では内容が異なります。
WISC-Vは、より現代の子どもの発達に合わせて評価方法が更新されました。
WISC-IVもまだ多くの機関で使われていますが、今後はWISC-Vへの移行が進むと考えられます。
対象年齢は、WISC-IVが5歳0ヶ月から16歳11ヶ月まで、WISC-Vが6歳0ヶ月から16歳11ヶ月までです。
検査を受ける機関がどちらのバージョンを使用しているか、事前に確認しておくとよいでしょう。
バージョンによって評価の観点が少し変わるため、大切なポイントとなります。
5つの指標と全検査IQで認知能力を多面的に評価できる
WISC検査は、子どもの認知能力を複数の指標と「全検査IQ」という視点から評価します。
これは、子どもの知能を単一のIQスコアだけで判断しないためです。
たとえば、広く普及しているWISC-IVでは「言語理解」「知覚推理」「ワーキングメモリー」「処理速度」の4つの指標が用いられます。
最新版のWISC-Vでは、これらが5つの指標に更新されています。
これにより、子どもの能力の得意分野と苦手分野を、具体的に把握することが可能です。
全体のIQと各指標をあわせて見ることで、その子に合った支援の手がかりが得られます。
WISC(ウィスク)検査の内容とは?WISC-Vの5指標を中心に解説
WISC-IVの「知覚推理(PRI)」指標が、WISC-Vでは「視空間(VSI)」と「流動性推理(FRI)」の2つに分かれました。
ここでは、WISC-Vで用いられる5つの主要な指標について紹介します。
| 言語理解(VCI) | 言葉による理解力や思考力を測る |
| 視空間(VSI) | 目で見た情報を正確に捉え空間的に考える力を測る |
| 流動性推理(FRI) | 新しい問題に対し論理的に解決する力を測る |
| ワーキングメモリー(WMI) | 情報を一時的に記憶し処理する力を測る |
| 処理速度(PSI) | 視覚情報を素早く正確に処理する力を測る |
それぞれの指標がどのような力を測っているのかを知ることで、検査への理解がさらに深まります。
言語理解(VCI)は言葉による理解力や思考力を測る
「言葉をどのくらい知っているか」や「言葉を使って考える力」を測る指標です。
学校の勉強や日常生活では、言葉を通して知識を学んだり、自分の考えを伝えたりする場面が多くあります。
この指標が高い子どもは、言葉の知識が豊富で、言葉による説明を理解したり、質問に的確に答えたりするのが得意な傾向にあります。
たとえば「〇〇と△△はどこが似ていますか?」といった質問に答える課題などを通じて評価します。
国語の読解力や、コミュニケーション能力の土台となる力といえるでしょう。
視空間(VSI)は目で見た情報を正確に捉え空間的に考える力を測る
目で見た情報を正確に捉え、頭の中で組み立てたり操作したりする力を測ります。
パズルや積み木、図形の模写などをイメージすると分かりやすいかもしれません。
この指標が高い子どもは、図形や地図を理解するのが得意な傾向にあります。
たとえば、モデルと同じ模様を積み木で作る「積み木模様」や、絵の欠けている部分を答える「絵の完成」といった課題があります。
これらの課題は、WISC-IVでは「知覚推理指標」に含まれていました。
算数の図形問題や、物と物の位置関係を把握する力に関係する指標です。
流動性推理(FRI)は新しい問題に対し論理的に解決する力を測る
初めて見る問題や新しい状況に対して、ルールを見つけ出し、論理的に考えて答えを導き出す力を測ります。
学校で習った知識というよりは、その場で考える「応用力」に近い能力です。
この指標が高い子どもは、法則性を見つけたり、物事の因果関係を推測したりすることが得意な傾向があります。
たとえば、いくつかの絵を見て仲間外れはどれか、またその理由を答える課題などがあります。
算数の文章問題や、プログラミング的思考にも関連する重要な力です。
ワーキングメモリー(WMI)は情報を一時的に記憶し処理する力を測る
情報を一時的に記憶し、その情報を使いながら別の作業を行う力を測ります。
「聞きながらメモを取る」「暗算する」といった活動を支える、いわば「脳のメモ帳」のような能力です。
この指標が高い子どもは、先生の長い指示を聞き取ってそのとおりに行動したり、順序立てて物事を考えたりするのが得意な傾向にあります。
たとえば、読み上げられた数字を反対からいう課題などがあります。
この力は、あらゆる学習や行動の基礎となる重要な能力です。
処理速度(PSI)は視覚情報を素早く正確に処理する力を測る
目で見た簡単な情報を、いかに速く、正確に処理できるかを測ります。
多くの情報の中から特定の記号を探したり、書き写したりするような、単純作業のスピードと正確さに関する能力です。
この指標が高い子どもは、黒板の文字をノートに書き写す作業や、単純な計算などをテキパキとこなすのが得意な傾向があります。
ただし、作業が丁寧で時間はかかるという子もいるため、この指標だけで作業能力のすべては判断できません。
学習の効率性に関わる指標の1つです。
WISC(ウィスク)検査のメリット

WISC検査は子どもの能力を評価するだけでなく、個性を理解し、可能性を広げるための第一歩となります。
ここでは、検査を受けるメリットを3つ紹介します。
- 子どもの特性を客観的に理解できる
- 家庭での適切な関わり方が分かる
- 学校や支援機関と連携しやすくなる
それぞれ見ていきましょう。
子どもの特性を客観的に理解できる
WISC検査の最大のメリットは、子どもの得意なことや苦手なことを客観的な指標で理解できる点です。
日常生活の中では、保護者の主観や「ほかの子と比べて」という視点が入りがちになります。
しかしWISC検査では、世界標準の基準に基づいて子どもの能力を分析。
そのため「うちの子は話す力は強いけれど、見た情報を覚えるのは少し苦手かもしれない」といった具体的な特性を、数値的な根拠と共に把握できます。
この客観的な理解が、子どもの個性を正しく認め、伸ばしていくための大切な一歩となります。
家庭での適切な関わり方が分かる
検査によって子どもの特性が明らかになると、家庭での具体的な関わり方のヒントが見えてきます。
たとえば、ワーキングメモリーの特性が見られるお子さんには、一度に多くの指示を伝えるのではなく、1つずつ伝えるなどの工夫が効果的です。
その代わり「まず〇〇をしてね」と伝えることで、子どもは混乱せずに行動できます。
子どもの認知特性に合わせた関わり方をすることで、親子のやりとりがよりスムーズになるでしょう。
関連記事:発達障害にカウンセリングは意味がない?期待できる効果は?
学校や支援機関と連携しやすくなる
WISC検査の結果は、家庭内だけでなく、学校や支援機関と連携する際の「共通言語」となります。
担任の先生や専門家に対して「うちの子はそわそわしていることが多くて」と感覚的に伝えられます。
加えて、「処理速度が平均よりゆっくりなので、板書を写すのに時間がかかります」と具体的に説明することも可能です。
客観的なデータがあることで、先生も子どもの状況を正確に理解し、座席の配慮や声かけの工夫など、個別の支援をしやすくなります。
家庭と学校が同じ方向を向いて、子どもをサポートする体制を築きやすくなるでしょう。
関連記事:発達障害におけるカウンセリングの効果はどのように現れる?
WISC(ウィスク)検査のデメリット
WISC検査には多くのメリットがある一方、事前に知っておきたい注意点も存在します。
ここでは、検査を検討するうえでデメリットや負担となる、以下3つを解説します。
- 検査結果の数値に一喜一憂するリスク
- 検査が子どもに与える心理的負担
- 検査にかかる費用と時間の負担
詳しく見ていきましょう。
検査結果の数値に一喜一憂するリスク
WISC検査は数値で結果が示されるため、その数字だけを見て一喜一憂してしまう可能性があります。
とくにIQの数値が平均より低く出た場合、保護者の方が驚かれたり、お子さんの将来について不安を感じられることがあります。
しかし、WISC検査の目的は子どもに点数をつけて優劣を決めることではありません。
大切なのは数値そのものではなく、その背景にある子どもの個性と、これからどうサポートしていくかという視点を持つことです。
検査が子どもに与える心理的負担
検査は通常、数時間にわたって行われ、子どもにとっては集中力と忍耐力が必要です。
知らない場所で知らない大人と一対一で課題に取り組むことに、緊張やストレスを感じる子も少なくありません。
とくに、答えが分からない問題が続くと、自信をなくしてしまう可能性も。
検査を受ける前には、子どもに「君の得意なことや苦手なことを知るためのものだよ」と目的を優しく伝え、安心させてあげることが大切です。
子どもの性格や当日の体調によっては、検査が負担になることも考慮しておきましょう。
関連記事:性格を変えるたったひとつの方法
検査にかかる費用と時間の負担
WISC検査を受ける機関によって、費用や時間に差があります。
たとえば、医療機関で医師が検査を必要と判断した場合は、健康保険が適用されることがあります。
一方、民間のカウンセリングルームや心理相談室では保険適用外の自費診療となることが多く、その場合の費用は1万円台から数万円が目安です。
公的な教育支援センターなどでは、無料で受けられる場合もあります。
時間的、経済的な負担については、検査を希望する機関に事前に確認しておくことが賢明です。
関連記事:カウンセリングを受けたいのにお金がないときの選択肢とは?
まとめ:WISC(ウィスク)検査を子どもの幸せにつながるために
WISC検査は、お子さまの認知能力を多面的に理解し、よりよい支援につなげるためのツールです。
検査結果から得られる複数の指標は、お子さまの特性を客観的に示し、家庭や学校での効果的なサポート方法を見つける手がかりとなります。
もしWISC検査の実施をご検討中でしたら、Heart Lifeでもお手伝いが可能です。
渋谷店では、公認心理師・臨床心理士によるWISC-V検査(対象年齢:6歳0ヶ月~16歳11ヶ月)を実施。
専門的な検査と、丁寧なフィードバックを提供しています。
検査料金は22,000円で、結果の解説を含むフィードバック面接と所見作成には、別途8,000円が必要です。
お子さまの特性を理解し、適切な支援方法を一緒に考えていきませんか?
この記事の監修者

横浜国立大学大学院臨床心理学専修卒業。卒業後、東京都市教育センターで発達に関する相談業務に従事。その後、神奈川県内の心療内科クリニックで心理士業務、東京都内心療内科・心理カウンセリングルームの心理士勤務を経て、2020年6月、渋谷・心理カウンセリングルーム「Heart Life~こころの悩み相談所~」を開業。2024年3月に「Heart Life~こころの悩み相談所~新宿店」を開業。
<公式SNS>YouTubeアカウント:「心理カウンセラー【臨床心理士】がうつ病について語るCh」
公式Twitter
公式Instagram